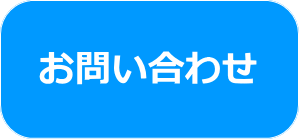SAS接続HDDのデータ復旧サービス
SAS接続タイプのHDDのデータ復旧はデータ復旧センターにお任せください。主にサーバー用のハードディスクとして使用されるSASインターフェースの故障やデータ消去などの障害について、専門技術による高精度なデータ復元サービスを実施しています。
一般的に対処が難しいとされるSASタイプのHDDもあらゆる障害に対処可能です。他社で復元できなかった案件もお気軽にご相談ください。
SAS接続タイプのHDDの特徴
SASとはSerial Attached SCSIの略であり一般的にサスと呼ばれるインターフェース規格です。ハードディスクは接続機器のタイプにより、様々なインターフェースを持ちます。パソコンや外付けHDD、BDレコーダーなどに幅広く使用されているのが「SATA」タイプのHDDです。一方、高処理能力が要求されるデータサーバーなどには「SAS」タイプのハードディスクが使用されています。SASはSATAに比べ、以下のような違いがあります。
| SAS-HDD | SATA-HDD | |
| 用途 | データサーバーなどエンタープライズ向け機器 | PC・外付けHDD・レコーダーなど汎用 |
| 処理速度 | I/O二重処理・高回転により高速 | I/O半二重処理・低回転により低速 |
| 形状 | 電源・通信が一体化 | 電源・通信が分離 |
| 互換性 | SATAへの互換性有り | SASへの互換性無し |
| 規格系統 | SCSI | IDE/ATA |
| 故障率 | 低い | 高い |
| 価格性 | 高価 | 安価 |
SATAインターフェースではSASを認識できない
SASとSATAは外観が似ていますが、SATAはIDE/ATA規格から発展したタイプに対しSASはSCSIから発展したタイプとなり、データ通信のプロトコルが異なります。そのため、SATA環境の機器にSASタイプのハードディスクを接続しても認識することはできません(SAS環境はSATAタイプのHDDを認識することはできます)。上述の通りSASはデータサーバー用途が中心であり、ハイエンドモデルなど一部を除き、一般的なPCのマザーボードはSASインターフェースをサポートしていないものが多いです。
SASとSATAを変換するためのケーブルなども販売されていますが、接続先がSATAインターフェースではSAS-HDDを認識することができないため、SATAインターフェース環境しかない状況でデータ復旧を行うことはできません。
SASタイプHDDのデータ復旧には専門的な技術・設備が必要
そのため、故障やデータ消失などの障害時において、一般的なPC環境ではSASタイプのHDDを操作することはできず、データ復元ソフトなどを使用することはできません。SASタイプのHDDを解析するにはSAS専用の設備や技術が必要となるため、SATA解析環境しかないデータ復旧業者には対応することができません。
SASタイプHDDのデータ障害原因
SASタイプのHDDは信頼性が高いとは言え、精密機器であることに変わりありません。ハードディスクの特性上、衝撃に弱いこともあり落下故障をはじめ様々な原因で故障します。故障原因は大別して「論理障害」と「物理障害」に分けられます。
論理障害
論理障害はソフトウェア面の障害であり、ハードウェアの故障を原因としない障害です。例として、以下のようなものがあります。
- データファイルを誤って削除した。
- 初期化をしてしまった。
- RAID崩壊によりファイルが正常に開けない。
- フォーマットエラーによりアクセスができなくなった。
物理障害
物理障害はハードウェアの故障が原因となる障害です。例として、以下のようなものがあります。
- 電源を入れても起動しない(通電しない)。
- HDDが認識せず、異音がする。
- 落下により衝撃を与えてしまった。
- SASカードがショートしてしまった。
データ復旧方法
SASタイプのHDDが故障したり、データが消失した場合の復旧方法をご説明します。故障・障害原因は多種多様であり、原因を突き止めた上でそれを解決するというアプローチが大切です。
※以下に記載されている内容は専門的な技術・設備を要し、失敗した場合はデータ復元確率が大幅に低下する場合があり、慎重に実施する必要があります。
論理障害のデータ復旧方法
論理障害に対するデータ復旧方法の一例をご紹介します。
データ消去・削除の場合
誤ってデータファイルを消去したり、ゴミ箱から削除した場合でもファイルを構成していた元データは記録装置上に残存している可能性があります。元データさえ残存していれば、それを基にファイルを再構成(=データ復元)できます。消去して間もないのであれば元データが残存している可能性が高いため、データ救出確率を高めるには速やかな対応が必要となります。
具体的な手法は多々ありますが、代表的なアプローチとして「ディレクトリ情報を復元し、復元対象のファイルのセクタ位置を確認、元データを回収してファイル化を行うこと」です。ディレクトリ情報が復元できない場合でも、全セクタを解析することにより消去データの復元が可能です。
フォーマットエラーの場合
SAS-HDDは一般的にサーバーで稼動しており、特定のファイルシステムで稼動しています。市販モデルサーバーの多くはext系やXFSなど、Linux系統のファイルシステムが採用されています。
ファイルシステムが破損した場合はフォーマットエラーとなり、サーバーアクセスできなくなります。フォーマットエラーを引き起こす原因は多種多様であり、原因究明が大切となります。一般的な対処としてファイルシステムの構造解析とエラー修復を実施します。
RAID崩壊の場合
RAID構成が崩壊した場合、データファイルが正常に認識できなくなるため、RAID環境を再構築する必要があります。構築方法を誤ってしまうとデータが破損してしまう恐れがあるため、慎重にRAID分析を行う必要があります。
具体的には、「ブロックサイズの特定」「ブロックの並び順の特定」「ブロック行数の特定」などを行い、ストライピングルールを分析した上でRAIDの再構築を実施します。
物理障害のデータ復旧方法
物理障害に対するデータ復旧方法の一例をご紹介します。
※物理障害の場合、安易にデータ復旧ソフトなどを使用すると急激に故障状態が悪化するケースが多々あります。異音がしたり、電源すら入らないなど物理障害が疑われる場合は無闇に操作しないことを強くお勧めします。
異音がする場合
「カチカチ」「カタカタ」「ジー」など、明らかに通常時と違う異音がする場合、HDDが物理的に故障しています。SSDの場合は電子記録媒体なので、異音はしません。異音が発生したHDDは正常に認識することができず、プラッタスクラッチなどの重度物理障害に発展する可能性があるため特に慎重な対応が必要となります。
異音が発生した場合、発生原因を突き止めて対処する必要があります。ヘッドが故障している場合はヘッド交換、スピンドルモーターが故障している場合はモーター交換などを行い、HDDが正常認識できるように対処します。
起動しない場合(認識しない場合)
HDDが起動せず、動作音もない場合は導通異常(通電異常)が発生している可能性があります。この場合、正常に電気が流れていない状態となるため起動することができません。このケースはホコリなどに引火し、火事の原因ともなるので注意が必要です。多くの場合、ショートなどの電気的故障が生じているケースがあります。データ復旧方法としては記録装置の状態確認を行い、導通ライン確立などの手法をもってデータ救出を行います。
SASカードの故障
SASインターフェースを実装する場合、MBに機能が無い場合はSASカード(HBA)を実装します。このSASカードが故障した場合、HDDへのアクセスができなくなります。また連動してHDDの論理障害が併発する可能性が高いため、HDDの起動時に全般的なプログラムエラーの確認を行います。
データ復旧サービスの費用・相場
多くのデータ復旧業者はSAS-HDDのデータ復旧サービスを提供していますが、費用・料金相場は業者によりバラバラです。データ復旧サービスは価格だけで比較できるものではありません。単なるデータ復旧ソフトを使用しているだけの業者もあれば、専門技術により高精度なデータ復元を提供している業者もあり、価格のサービス品質が連動していないからです。
その技術水準は業者によりばらつきがあります。前述の通り、SAS-HDDのデータ復元は専門技術が必要となるため、技術力の低いデータ復元会社を選択してしまうとデータ復旧に失敗するどころか二度とデータが救出できなくなるリスクがあります。
データが重要な場合、費用面も大事ですが何よりも技術力を重視し、安心できるデータ復旧サービスを選択されることをおすすめします。
データ復旧センターでは高度な技術力により、他社復旧不可案件を中心に高精度なデータ復元を実施しています。料金のお見積もりなどをご希望の方はお気軽にお問い合わせください。